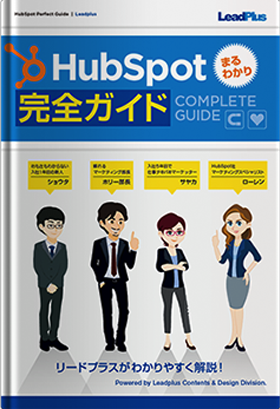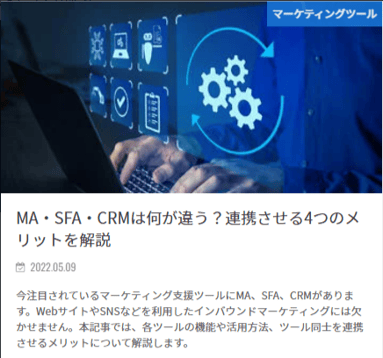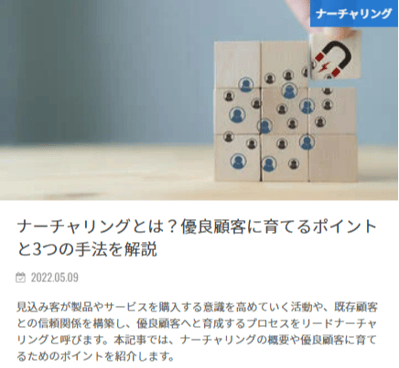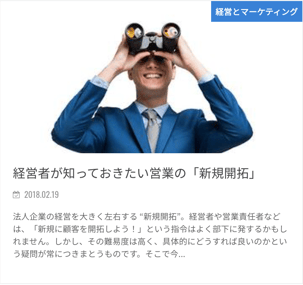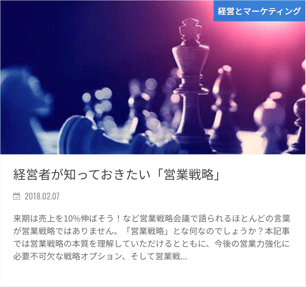SFAとは?CRMとの違い
今でこそSFA(営業支援システム)は一つのシステムとして広く浸透していますが、そもそもは“営業を科学的に分析し支援するための概念”です。ちなみにSFAという言葉自体は「Sales Force Automation」の頭文字を取ったものです。
1993年に創業されたシーベル・システムズ(2005年に米Oracleが買収)がSFAアプリケーションをリリースしたことで、米国を中心に爆発的に普及しました。
海外のトレンドが数年遅れで日本に上陸するという例に漏れず、1990年代後半から国内でもグループウェアと共に普及が始まりましたが、当時の伸びゆきは悪かったようです。
理由としてはまず、日本は欧米ほどネットワーク環境が整備されていなかったこと。そしてITスキルを有した人材に乏しかったことが挙げられます。
しかし最も大きな理由はおそらく、それまで「勘」「根性」「経験」で築き上げられてきた日本の営業文化に受け入れられなかったのでしょう。その後は日本企業のグローバル化が進んだことと、SFAの進化により現在の普及に落ち着いています。
SFAの得意領域
- 顧客データ管理(三層管理)
- 売上げなどを可視化するレポート機能
- 全体でタスクを共有できるToDo機能
- 見積書・請求書などの帳票類作成機能
- 日報作成・管理機能
SFAの得意領域名刺管理システムも一種のSFA?
営業の現場において最近普及され始めた名刺管理システムですが、テレビCMなども放映されていることからニーズが急速に拡大しています。そして名刺管理システムもSFAの一種として捉えている企業が多くなりました。
というのも、実際に各サービスを見てみると名刺管理以外にも案件管理やToDo機能などを備えているシステムが多く、簡易的なSFAを提供していることが多いんです。
むしろ名刺管理システムをSFAとして利用する方が「シンプルな機能と操作性で使いやすい」といった声が増えています。
SFAとCRMの違い
SFAとよく比較されやすいシステムに「CRM」が挙げられます。ここではSFAとCRMの違いに関する基礎知識をお伝えします。
図解で表すと下記のようなイメージです。

CRMとは
CRMは、営業マンが獲得した顧客との関係を維持・向上させるシステムです。「Customer Relationship Management」の略称から名付けられ、日本語では「顧客管理システム」と呼ばれています。CRMを導入する目的は、既存顧客の継続的な商品・サービス利用を促進することです。
主にカスタマーサポート部門の業務で役立てられています。CRMを活用すると、データ分析によって顧客理解が深まり、ターゲットのニーズに適したマーケティングを実現しやすくなります。また、既存顧客と良好な関係を維持するため、効率的にアプローチする機能が充実しているのも特徴です。
CRMでできること
- 顧客データ管理(二層管理)
- 既存顧客・見込み客へのメール配信
- アンケートフォームによる満足度調査
- セミナー・イベント管理機能
- 顧客対応を中心としてCTI機能
SFAとの違いを見てみるとSFAの方が営業に特化したシステムであり、CRMは全社的に顧客情報を管理するためのシステムと捉えることができます。事実SFAは「売上げの最大化」そしてCRMは「顧客満足度向上」を目的に導入されることが多いです。
しかし最近になって両者の境界線が曖昧になりつつあります。全ての機能を包括してサービスのリリースが盛んになり「SFAを包括したシステムがCRM」という傾向が強くなっているようです。
また、CRMによってはマーケティングプラットフォームのHubSpotと顧客デーたを連携することができます。HubSpotについてまとめたEブックを準備しています。ご興味があれば合わせて以下をご確認ください。
SFAを導入する目的
SFAとを導入にあたり目的の明確化は必須です。代表的な目的として以下の3つが挙げられます。
- 売上の向上
- ノウハウの共有
- 営業プロセスの見える化
- SFAを導入することで教育コストを軽減する
1つ目の「売上の向上」が最大の目的で、2~4つ目はそれに至るためのマイルストーンのようなものと言えます。それぞれ詳しくご紹介します。
1. 売上の向上
売上を向上させることは企業全体の目標でもありますが、SFAを導入することで売上が向上する可能性がぐっと広がります。
例えば、SFAから得られる営業の行動管理データから、本人も意識していないインサイトを分析することで、ボトルネックになっている部分を見つけ出し、売上アップに繋がる行動に改善していくことができます。
2. ノウハウの共有
営業活動は属人化しやすいと言われがちですが、担当が変わってもすぐに引き継げる環境や、営業チーム全体が同じように優秀な成績を挙げられる体制を築くことは非常に重要です。
SFAでは、営業が顧客の社内のメンバーとやり取りしたメールや提案資料、アプローチ方法、ヒアリング内容が全てログとして残るため、これを参考にして有効なナレッジやスキルを効率よく共有することができます。
わざわざ資料を共有したり、できる人がマンツーマンで教えたりという手間がかからないため、最小のコストで最大限の効果を上げることができます。
3. 営業プロセスの見える化
営業プロセスの見える化とは、リード(見込み顧客)の獲得からそのリードへの訪問や商談を経てクロージングに至るまでの一連の営業プロセスを可視化することをいいます。
SFAを導入することで、以下のようなデータを見える化することができます。
- 顧客の予算や競合情報・見積書提出・デモの実施など、案件がフェーズにあるか
- 必要なアクションが行えているのか
- 各営業が、どのような内容の営業活動をし、どのくらい時間をかけているのか
こうした数字をいつでも簡単に確認できるため、案件の進捗や営業全体の進捗の可視化、次に何をすれば成果が上がるのかまで特定できます。
例えば、直近4ヶ月売上を伸ばしているAさんと、一向に売上が挙がらないBさんのデータを比較分析することで、売上が挙がらない原因を特定し、改善策を立てたり、勝ちパターンを見つけたりできます。
さらに獲得した顧客を伸ばすポイントについて以下で解説しています。
4. SFAを導入することで教育コストを軽減する
新しい営業メンバーを採用すれば、全体の売上は上がります。
しかし戦力化するまでには、既存の営業メンバーによる研修など多大な教育コストがかかってしまいます。
教育や研修はたしかにマンパワーで解決できることかもしれませんが、既存の営業メンバーが教育に時間を取られることで売上が下がる可能性も高く、教育コストは意外と侮れません。
営業で主に教育コストがかかるのは、下記3つになります。
①セールストークなどの指導 ②営業資料の共有 ③案件に関する情報共有
SFAを導入することで、このうち②と③を解決することができます。
過去に送ったメールや提案書、顧客企業の担当者情報・やり取りなどを残すことができるため、情報共有にかかっていた時間を大幅に削減できるのです。
教育コストの削減については、売上を上げるのではなくコストを軽減して結果的に利益に繋げることが主目的となります。
加えて、新しい営業メンバーをいち早く「売れる営業」に育てることで、売上を上げるという目的にも繋がります。
SFAの主な8つの機能
SFAとは営業支援システムですが、例えば営業活動を記録するのみならExcelでも可能です。そこでSFAだからこそできる、以下の8つの機能を確認していきましょう。
①顧客管理
②案件管理
③見積書作成
④行動管理(プロセス管理)
⑤売上予測・予実管理
⑥スケジュール・タスク管理
⑦日報・週報
⑧集計・分析レポート

1. 顧客管理
CRM(顧客管理システム)はもちろんですが、SFAにおいても、顧客の情報の取得・管理は最重要事項であり、SFAも顧客情報を一元管理する機能を備えています。社名や所在地、連絡先、担当者名、担当者の属性情報のほか、問い合わせや取引履歴などの情報を一元管理し、社内で共有することで、営業担当者が重複セールスをしてしまったり、担当者変更時に引き継ぎができていなかったりといったミスを防ぐことができます。
2. 案件管理
案件管理とは、各案件の詳細情報を一元管理する機能です。従来の営業手法では、各案件の詳細は担当者しか知らないことも多く、担当者が不在のときの対応に不備が生じたり、営業が個人の経験や勘に頼ったものになったりしがちでした。
案件管理により、各案件の進捗状況を見える化することで、組織としての営業ノウハウを蓄積。過去の商談履歴や内容を分析して、最適なアプローチ法を導き出すことができます。
また、データを入力する時に限りなく整合性のある情報に整えるにあたっては、営業プロセスを標準化をする必要があります。具体的には「何を案件として登録するのか」「案件確度」などをルール化することでより正確に今期の売上予測が立てやすくなるでしょう。
3. 見積書作成
時間をかけず、迅速に見積書を発行する機能もSFAに備わっています。情報も一元管理されているため、顧客の購買意欲が高まっているタイミングを逃さず見積書を示すことで成約の可能性を高め、顧客が競合他社に流れてしまうのを防ぎます。
4. 行動管理(プロセス管理)
行動管理とは、営業担当者の業務プロセスを見える化し、管理するための機能です。定量面では、テレアポのコール数や訪問数、商談回数、成約率などの行動と結果を数値化して管理します。定性面では、テレアポでの会話ログや商談の詳細な対話ログも管理することが可能なので、若手メンバーが聞くべきポイントを聞けているかなども確認することもできます。また、売上目標が達していない場合に各担当者のボトルネックの発見にも役立ちます。
5. 売上予測・予実管理
SFAには、営業担当者ごと、部署ごと、顧客ごと、商品・サービスごとなど、様々な基準から売上予測と実績を可視化する機能があります。予測と実績の比較も簡単になりますので、目標到達度の測定もスムーズに行うことができます。
6. スケジュール・タスク管理
スケジュールを一元管理する機能により、管理者の営業マネジメントに役立ちます。また、営業担当者同士で予定を共有することで、より効率的な連携を可能にします。
タスク管理は、各営業担当者が優先度の高い仕事に集中するのに役立つほか、管理者によるタスクマネジメントにも活用でき、全社的にも良い方向に売上がシフトする可能性が上がるでしょう。
7. 日報・週報
日報や週報は、日本の商習慣に合わせて組み込まれている機能です。特に、新卒や新入りの中途社員には目配りがより重要となります。管理者が各営業担当者の行動や成果を把握し、管理するのに役立ちます。
8. 集計・分析レポート
SFAの中には、AIによるデータの分析・集計レポートの作成機能まで備えているものもあります。商材別、エリア別など、様々な角度から分析することができ、レポート作成も可能なので、会議資料の作成などにも役立ちます。
また、分析レポートを元に受注分析や失注分析もできるため、今後の戦略決めの際にも役立ちます。
SFAのメリット・デメリット
ここからは、SFAを利用するメリット・デメリットについて説明します。
現場/ マネージャーから見たメリット

1. 商談のステージを管理することで次のアクションを明確に示す
SFAの特徴と言えば顧客データの三層管理であり、顧客情報と案件情報の二層管理に加え商談情報を管理することができます。
商談情報が管理される以前は「勘」「根性」「経験」がものを言う世界だったのですが、現在では情報をもとに管理がなされているので次のアクションを明確に示すことが可能となりました。
これにより営業活動の効率化やセールスのタイミングなどを正確に掴むことができ、利上げの最大化に貢献しています。
2. ナレッジが蓄積することでベストプラクティスを生み出せる
案件情報や商談情報をシステムに蓄積していくことで、そこには自然と営業ナレッジが蓄積されていきます。しかも、好きな情報を簡単に抽出することができるので非常に効率的です。
こうしたナレッジを分析することで営業のベストプラクティスを生みだし、部全体で共有すれば営業スキルの底上げにもつながるメリットがあるのです。
3. 営業日報をシステムに組み込むことで業務効率化が促進する
SFAの基本システムである営業日報もまた、業務効率化に貢献する機能の一つです。これまではExcelで作成した日報を印刷して上司に提出するといったケースが多かったでしょうが、システム上で報告を行うことで印刷と提出の手間を省くことができます。
もしもSaaS型(※1)ならば上司は外出先から日報を確認することができるので、場所と時間を問わず円滑なコミュニケーションが可能です。
その他タスクやスケジュール等も共有できるので、営業活動がより加速します。
※1:SaaS型とは「Software as a Service」の略であり、インターネット経由で利用するシステムやサービスを指す。オンラインストレージなどが代表的。
4. 営業活動が見える化される
- 顧客の予算や競合といったデータ
- 見積書提出、デモの実施など、案件がどのフェーズにいるのか
- 必要なアクションが行えているのか
- 各営業が、どのフェーズや行動に時間をかけているのか
以上のようなことを把握できることで、受注確度の判断やより的確なアドバイスができます。
5. イレギュラーを発見しやすい
進捗が止まったままの案件や、値引額が大きすぎるなど、通常とは違う状態の商談や案件を、早期に見つけることができます。
見つけ次第すぐに、原因を分析して見直しや改善をすることで、最小限の影響(被害)に留めることができます。
6. 数字をすぐに把握できる
業績報告や会議の際には、数値レポートが必要になります。
各営業メンバーへのヒアリングや日報から拾ってくることもできますが、これにはかなりの時間と労力がかかります。
SFAであれば、定形フォームへの入力が多いので、内容に大きなばらつきが出ることがなく、数値データを簡単に集計・分析することができます。
これまで2時間ほどかかっていた集計作業が、たった4分でできるようになったという事例もあります。
経営層から見たメリット

1. 経営戦略の立案に活かせる
市場や顧客、組織全体の状況が一つのツールにまとめてあるので見やすく、リアルタイムで分かるので、情報に基づくスピード感のある経営判断ができるようになります。
例えば、他業種の顧客が増えても、何がボトムネックで受注・失注が多いのかなど、簡単に集計することが可能です。
2. 教育コストの削減
通常、新人は先輩がやっていることを見たり、分からないときは質問をしながら、時には上司が付きっ切りで面倒をを見ながら、仕事を覚えていきます。
悪いやり方ではないのですが、上司にはかなりの負担がかかります。
しかし、SFAを導入することでナレッジの共有ができるようになれば、上司に聞かなくても、提案資料や行動の勝ちパターンを学ぶことができます。
3. マネジメント層の適正な評価ができる
現場は売上で評価をすることができますが、マネジメント層は売上に直結しない業務が多く、適正な評価が難しいです。
どれだけ案件のサポートに入ったのか、営業のボトルネックを解消できたのかは簡単に数値化することができないため、評価が難しくなってしまいます。
SFAで営業のプロセスが見える化されることによりマネジメントの中身が見え、経営者が適正な評価ができ、それがマネジャーのモチベーションアップにも繋がります。
■関連記事はこちら
共通のデメリット
導入・ランニングコストがかかる
無料で利用できるオープンソースSFAはあるにはあるのですが、やはり本格的に利用するとなるとパッケージかSaaS型を導入することになると思います。
パッケージ型は自社サーバの設置やインストールなどの費用がかかり、導入だけで数百万円かかることは珍しくありません。また、サーバやシステムの管理・運用費などもかかります。
SaaS型では初期費用が数万円程度と安価なので導入費こそかからないものの、ユーザー数に応じた月額料金が発生します。
長期的な目線で見るとパッケージ型のコストを上回るケースもあるので、導入後の利用完了を考慮した上でトータルコストを比較することが大切です。
SFA導入でありがちな4つの失敗パターン
導入することでメリットが多くあるSFAですが、ここではSFA導入時にありがちな「失敗4パターン」を紹介していきます。
導入したにも関わらず、社内に浸透しないという最悪なケースを引き起こさないよう、事前準備に失敗パターンを確認しておきましょう。
1. 「SFAの使用」が目的にならないよう注意する
SFAの導入後、いつの間にか使用することが目的になってしまうと、自社が期待する効果を実感することは難しいでしょう。システムの定着を促すために、日常的なSFAへの情報入力は欠かせません。しかし、入力するだけでは、自社の課題を解決できないのです。
SFAの使用がゴールにならないよう、PDCAサイクルを継続的にまわしましょう。
案件の取りこぼしを無くすことで想定される最大限の売上にどの程度近づいたのか、営業活動の内容を評価して改善点を把握し、それをもとに活動をアップデートしていきましょう。この取り組みを組織ぐるみで行うことが重要です。
2. 営業に嫌われ使用されないシステムとなった
SFAはブラックボックス化されている営業情報を可視化するためのシステムなので、現場の営業マンからすれば現状より多くの情報を上部に提出することになります。
ここで営業マンが考えるのが「業務負担が増加する」と「今後評価が厳しくなる」というこです。
現場からすれば業務負担が増加することと評価が厳しくなることはご免被りたいことなのですが、会社の方針とあらば従うしかありません。しかし次第に使用されなくなり、リスト管理のためのシステムとなってしまったというパターンは非常に多いのです。
SFA導入の目的と業務効率化の指南、そして評価システムへの影響などを予め説明し、理解を得てから導入することが大切でしょう。
3. 経営陣や情シス中心で導入したため現場に馴染まなかった
システムを導入する以上経営陣と情シスが絡むのは仕方のないことですが、あくまでSFAを利用するのは現場の営業マンです。
現場を無視して導入してもシステムとして機能することはおそらくないでしょう。導入検討段階から現場責任者を巻き込み(むしろ中心にして)、現場の声をしっかりと反映させた導入が非常に重要です。
4. いきなりフル機能で導入して扱い切れなかった
これもよくある失敗パターンで、SFAは基本的に高機能なのですぐに全てを使いこなすことは難しいシステムです。ましてや営業マンごとのITスキルにムラがあればシステムに慣れない者が出てくるのも当然でしょう。
意外なのが、成績トップの営業マンほどSFA導入で潰れやすいということです。実は仕事ができる人ほどスケジュール管理を手帳で行っていたり、アナログ人間が多いのでシステムの利用を強要されるとペースが崩れてしまいます。
こうした理由から会社のエースストライカーを失ってしまうケースも多いので、注意が必要です。しかも、システムを導入したからといって急激に成績を伸ばす者が出てくるわけでもないので、売上げが大きく落ち込む原因にもなりかねません。
SFAの導入は少しずつ、スモールスタートで徐々に拡大していくのがセオリーです。
SFA導入で失敗しないための3つのポイント
失敗事例をご紹介した次は、導入で失敗しないためためのポイントを3つ、ご紹介します。
1. 導入目的と課題が明確になっている
誰が、どのように使って、どんな成果を挙げたいのか、そしてそれがSFAの導入でかいけつできる、と納得できてから導入しましょう。
2. 価格と機能のバランスがいい
SFAを導入するには、多くの費用がかかります。例えば、初期費用がある場合、まとまった金額とが必要になります。また、オプションサービスなどを利用すると、これに加えて追加費用を支払う可能性も考えられます。
さらに、運用開始後は毎月の月額費用が発生するのが一般的です。月額費用は、アカウント数に応じて料金が高くなることも。年間で必要となるランニングコストも確認しておくと安心です。SFAに投資した費用に対して、営業部門で十分な効果が得られるかを重視しましょう。
3. 使い勝手がいい
UI/UXが良いとか評判が高いという基準だけでなく、実際に導入後に使う現場の営業マンが操作しやすいツールを選びましょう。特に最初のうちは、導入準備や運用開始直後に、社内で業務負担が発生します。例えば、設定や運用ルール策定といった作業です。
また、導入後にSFAが定着するまでには、一定の時間がかかります。操作に慣れるまでは、現場の負担が大きくなるケースも少なくありません。これらの業務負担を踏まえたうえで、システムの導入を検討しましょう。
以上3点が、最低限、気をつけるポイントになります。またツール別に比較したい方は、「【マーケ担当者必見】プロセス別おすすめマーケティングツール14選!」もご覧ください。
SFA導入の2つの成功事例
ここでは、SFAを実際に導入すると、どのような成果が出るのか2つの事例を見てきます。
1. 業種:製造業 会社規模:11~30名
SFAを導入に成功したA社は、社内の全ての営業情報をSFAで一元管理しています、以前はExcelファイルで理行管理を行っていましたが、業務効率化・ナレッジの共有を目的にSFA導入を検討しました。Excelの管理方法を廃止するために、A社は導入準備の段階で作業マニュアルを作成し、勉強会にてレクチャーを実施。
全社的な取り組みの結果、20代~60代の幅広い年代のスタッフが所属する社内でSFAを定着させることに成功しました。営業部門の生産性向上や、マネジメントの実現した成功事例です。平均年齢が高い会社でも、丁寧に導入準備を進めればシステムを定着させられる可能性があります。
2. 業種:サービス業 会社規模:300~500名
SFAを導入に成功したS社では、SFAを外部システムと連携し、速やかに情報共有する体制を整えています。S社がシステムを選ぶ上で重視したのは、カスタマイズ性です。現場からの要望に答えながら調整を重ね、自社の業務に合った最適なカスタマイズを実装していきました。
その結果、SFAの導入後は従来よりも情報共有の手間が削減され、会議における進捗確認の効率化を実現しました。また、会議の議事録もSFAに連携したことにより、会社全体への情報共有もシームレスに。これらの工夫によって、本当に重要なコア業務外の仕事を50%以上削減することに成功しています。
お役立ちコンテンツについて
SFA導入/営業力強化を目指している方に対して、ホワイトペーパーや他記事もご用意。よろしければ、ご活用してください。
関連コンテンツ
SFAの投資対効果を最大化するMA連携
SFAはMAと連携することで、さらに効率良く導入することが可能です。MAの主な機能やSFAと連携するメリット、連携時の注意点について確認しておきましょう。
1. MAとは
MAとは、マーケティングに関係する業務を自動化し、効率を上げるツールのことです。
SFAとMAを連携することで、営業チームの出番となる前段階の見込み顧客の獲得から、顧客の育成プロセスやフォローまでを自動化することが可能です。
打ち合わせはしたものの案件化しなかった場合や、検討中止や失注になった場合のフォローも自動化できるので、関係を維持し、再度アプローチをすることができます。
例えば、案件化しなかった見込み顧客が、再度ウェブサイトで資料請求などを行ったことを察知できるので、的確なタイミングや内容でアプローチが実施できるのです。
MAツールの主な機能として、できることはいくつかあります。
MAの詳細については「【マーケター必見】MA(マーケティングオートメーション)の教科書」でも詳しく解説しています。参考にしてください。
2. SFAとMAの連携=営業とマーケティングの双方にメリット
従来の営業・マーケティング手法では、営業部門とマーケティング部門の連携が上手くいかず、営業部はマーケティング部に「見込み顧客の質が悪い」と不満を抱え、マーケティング部は営業部に「成約寸前の見込み顧客以外は、しっかり対応してくれない」といら立ちを感じる......といったことが起こりがちです。SFAとMAの連携は、このような両者の対立を解消するのにも役立ちます。
具体的には、両ツールの連携により、営業担当者はいつでも、担当する顧客がどこから自社と接点を持ったのか、自社サイトのどのページを何回見ているのか、マーケティングの段階でどのようなチャネルでどのようなやりとりがなされてきたのかなどを確認できます。担当する顧客がどのようなことに関心を持たれているのか、リサーチをされているのかをデジタルで把握することにより、顧客一人ひとりに合わせた効果的なアプローチが可能となります。
一方、マーケティングの担当者も、営業部に紹介した後の商談の様子をいつでも確認できますし、SFAでの活動履歴をトリガーにしたMAでのフォローアップ施策などを展開することができます。
営業とマーケティングの業務プロセスや成果が見えやすくなることで、「マーケティングは会社の売上に貢献していない」「営業はマーケティングが引き渡した見込み顧客を無駄にしている」といった不満も、解消されることが期待できます。
SFAとMAの連携は、営業とマーケティング双方にメリットをもたらすのです。
3. SFAとMAの連携時の注意ポイント
SFAツールやMAツールによっては、相互連携ができないものもあります。
連携を考えている場合は、必ず導入前に仕様を確認し、連携可能なツールを選んでください。
導入の目的を把握してからSFAを導入しよう
SFAを導入する目的は以下の3つです。
- 売上の向上
- ノウハウの共有
- 営業プロセスの見える化
SFAの導入時はシステムの価値を社内全体へ周知し、使用することが目的にならないようにしましょう。そして、価格・機能のバランスが良さや使い勝手が良いなど現場社員が使いこなせることを重視してSFAの選定することをおすすめします。
導入目的を明確化し、自社に最適なSFAを選んでください。
SFAを検討しているならHubSpotがおすすめ
SFAツールを業務に取り入れることで、売上の向上、ノウハウの共有、営業プロセスの見える化など、現場にとってさまざまなメリットがあります。
そこで、SFAやMA、CRMなど、営業組織やマーケティング部門が連携してインバウンドマーケティングに取り組めるツールが「HubSpot」です。
HubSpotは、世界120カ国以上・12万社以上の顧客が利用する世界最大級の営業管理ツールです。HubSpotは5つの機能から構成されており、インバウンドマーケティングの一連の流れである見込み客獲得から顧客の満足度向上までを、一元管理できます。
その中でもSFAに特化した機能が「HubSpot Sales Hub」です。営業活動を効率化するための見込み客とのコミュニケーションツールや情報提供ツールが揃っています。営業案件の進捗についてパイプライン管理をし、担当者の生産性とパフォーマンスを記録したり、取引の予測をしたりできます。
HubSpot Sales Hubを利用することで、煩雑な作業に追われる時間を顧客に使うことができるため、サービスや成果の向上が期待できます。営業活動をスリム化したい場合は、HubSpot Sales Hubの導入をぜひご検討ください。
HubSpot Sales Hubで営業部門の効率化 機能やプランの選び方
HubSpot Sales Hubの機能については「HubSpot Sales Hubで営業部門の効率化 機能やプランの選び方」でも詳しく解説しています。参考にしてください。
まとめ
今回色々とSFA(営業支援システム)について解説しましたが、営業に欠かせないシステムであることが分かって頂けたでしょうか。特にビッグデータの活用が叫ばれてる現代ビジネスでは、顧客から吸い上げられる情報は一つの金脈でもあります。
日々蓄積されている営業情報をマーケティングで企画開発へ打ち上げ、上手に活用することができれば、SFAの効果を最大限に引き出せることでしょう。
また、最近ではマーケティングオートメーションとの連携が重要視されており、今や現場の営業マンだけのシステムではなくなっています。ですのでSFAの導入検討をする際は広い視野でプロジェクトを推進していくのがおすすめです。
成長していく企業とは多様化する顧客ニーズと複雑化するタッチポイントを制し、営業とマーケティングを俯瞰して適切なシステムの選択と導入を成功させた企業なのかもしれません。
CRMと連携ができるマーケティングシステム「HubSpot」についてご興味ありませんか?以下のEブックではHubSpotの概要をコンパクトにまとめました。ご興味があれば合わせてご確認ください。